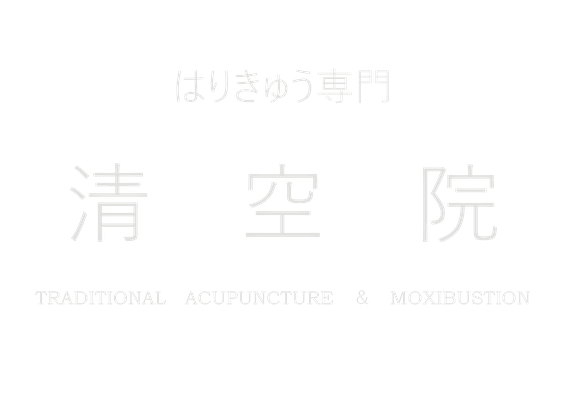当院の花壇にミントの花が咲きました。
植えた覚えない・・・(-_-;)
涼しげな花で、葉を潰すと爽やかな香りがしますが、恐ろしい勢いで増殖して、他の植物を駆逐する厄介者らしい・・・(;'∀')
麻杏甘石湯は、肺で悪さをしている熱を取る、と書きましたが、ちょっと混乱しそうなので補足。
麻杏甘石湯の出典は『傷寒論』です。
出典の流れからいっても、麻杏甘石湯は「風寒邪」の治療が上手くいかなくて「肺に熱がある」状況に追い込まれた時に使う薬です。
あれ、風寒邪で熱??? とここまでの話からすると「?」ですよね。
風寒邪は確かに「さむけ」を起こす「さむいさむい」という風邪ではあるのですが、風寒邪を受けた人体がやられっぱなしなわけがありません(やられっぱなしな状態は免疫不全の状態。風邪が命取りになってあっという間に死んでしまいます)。
いったん人体表面に取りついた風寒邪は、体表を守っている「衛気」と呼ばれる人体の防衛機能を一時追いやるため、衛気による保温機能(気の温煦作用といいます)が失調して「さむけ」が起こりますが、これを追い出すために衛気が体表に集まり、風寒邪と衛気とが衝突して発熱が起こります。
とりついた風寒邪が強烈であればあるほど、人体の衛気もフルパワーで戦おうとするので、発熱も尋常じゃなくキツイこともあります。
ところが表面での戦いがうまくいかず、麻杏甘石湯のケースのように肺まで風寒邪が入り込んでしまうと、、、
風寒邪が今度は一転して「熱邪」となり、肺を荒らしていきます。
風寒の邪が熱をおこす詳しい経緯は、私も少し調べ直したのですが、
「人体の衛気と風寒邪の衝突が熱邪を生む」
というのが、体表での現象で、
「体内に入ってくると邪そのものが「熱化」する」
と考えて良さそうなのですが、今ひとつはっきりさせられませんでしたm(_ _)m。
おそらく体内に侵攻してきたステージでも「衛気との衝突での熱」というのはあるようです。
傷寒論の考え方の基本にあるという説もあるのが『黄帝内経』の『素問』熱論(31)ですが、この中の条文、
黄帝問曰。今夫熱病者。皆傷寒之類也・・・
これについて江戸末期の森立之(1807--1885)先生の著書には、
凡邪気入於肌肉。必與血氣相搏。故発熱。(『素問攷注』)
という注釈を入れておられ、ここでいう「傷寒」とは風寒邪によるものだけでなく、「温病」によるものも含む、という考え方らしいのですが、いずれにせよ、外界から病気を起こしうるものが入ってきたら、必ず熱が起こる、と考えていいと思います。
肺だけでなく、表面から体内に邪が入るのを「裏(り)に入る」と言いますが、邪が裏に入ると多くの場合「熱化」するので、
どっちにせよ、治療は熱を冷ます、という方針に変わります。
邪が裏に入って熱による悪さが本格化するステージを『傷寒論』の中では「陽明病」と呼んでいますが、これはまた別の機会に。
(麻杏甘石湯は「無大熱」の条文があることで、陽明病に似ているが、ギリギリ陽明病ではない太陽病のステージとされます。)
ところで、熱を冷ます、という麻杏甘石湯の性質からでしょうか。
この方剤は、はじめから「暑邪」による病気「温病」を治療する中でも登場します。
(出典は『温病条弁』)
こちらでも汗が出て、咳がある場合、発熱があり、さらにものすごく口が渇き、胸が苦しくて呼吸困難、という状態の時に用いるようです。
温病だと、より「熱々しい」所見がハッキリしますね。
さて、最初の話に合った五虎湯ですが、これは麻杏甘石湯に「桑白皮」が入ったものと書きました。
桑白皮は、現代中薬学(中国の漢方)では、
「瀉肺平喘」「利水消腫」といって、肺の中の熱を去り、停滞している水を巡らせる作用を持つとされます。
性質が「寒」なので、麻杏甘石湯の「肺の熱を去る」という作用を更に強化する目的で入れたのかな??
ついでに漢方の原典ともいえる『神農本草経』では、
桑根白皮、味甘寒、生山谷、治傷中五労六極羸痩、崩中脈絶。補虚益気。
葉、除寒熱。出汗、桑耳、黒者、治女子漏下、赤白汁血病、癥瘕積聚腹痛、陰陽寒熱、無子。
とあり、疲労からくる内蔵の病や、女性の不正性器出血・帯下の異常などにも使われるようですね。
鍼灸なら肺経(肺と連なる経絡)の調整が入ってくるのかな。。。
(参考図書)
基礎中医学
中医病因病機学
中医臨床のための中薬学
中医臨床のための方剤学
中医臨床のための温病学
傷寒雑病論
神農本草経解説
中国傷寒論解説
素問攷注
現代語訳黄帝内経素問
中医四部経典