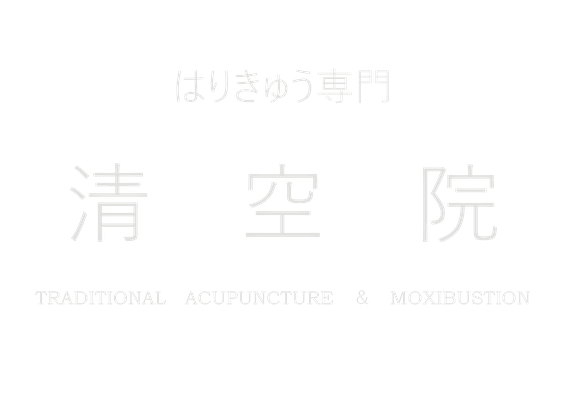前回は「破瘀行血」の桃仁について、勉強しました。
今回は牡丹(ボタン)について。
牡丹は書いて字のごとく、牡丹の花…の「根っこの皮」が実際に使われます。
なので「牡丹皮」(ボタンピ)という生薬名が現在では一般的。
『神農本草経』を読んでみましょう。
”牡丹、一名鹿韭、一名鼠姑、味辛寒。
生山谷。治寒熱中風、瘈瘏痙、驚癇邪氣。
除癥堅瘀血留舎腸胃。安五臓、療癰瘡。”
…牡丹、一名鹿韭(ろくきゅう)、一名鼠姑(そこ)、味は辛、寒。
山谷に生ず。寒熱中風、瘈瘏痙、驚癇邪気を治す。
癥堅瘀血、腸胃に留舎するを除く。五臓を安んじ、癰瘡を療す。…
…なんだそうです。
ここでも大事なのは
「除癥堅瘀血留舎腸胃」=癥堅瘀血、腸胃に留舎するを除く。
という所でしょうか。
さらに条文のアタマで「味辛寒」とあります。
前回の桃仁は「味苦平」でした。
辛く寒い「味」とは、ここでは「性質」という程度に考えておくとわかりやすいかもしれません。
「辛い」ものは「発散させる」の性質があり、さらに「寒」い、つまり冷やすんです。
(※一方、「平」というのは、「寒熱どちらにも偏らない」)
明代・李時珍(1518-1593)著『本草綱目』の中で、牡丹について、
「…和血生血涼血、治血中伏火、除煩熱」
(血を和し、血を生み、血を涼うし、血中の伏火を治し、煩熱を除く)
・・・という記載があり、
ちょっと時代が飛んで、本邦・幕末の浅田宗伯(1815-1894)先生著『古方薬議』では、
「味辛寒。癥堅瘀血を除き、癰瘡を療し、月経を通じ、撲損(打撲傷)を消し、腰痛を治し、煩熱を除く」と記され、
また前述の「血を和し、血を涼うし、血中の伏火を治し、煩熱を除く」という文献も引用されて記されています。
この「和血生血涼血、治血中伏火、除煩熱」というのが牡丹の要点でしょうか?
前回の桃仁は「破瘀行血」といって、瘀血を下す、しかも停滞して頑固なものを破壊するのがメインでしたが、
今回の牡丹は「清熱涼血」。
つまり「滞った血が帯びている悪い熱を追い出す」作用がメイン。
この作用、「透達」(=奥から表面まで、フワーッと散らす感じ?)という表現がされますが、
ここで桂枝茯苓丸の条文の始まりに戻ります。
「婦人宿有癥病」
”婦人宿(もと) 癥病(ちょうびょう)有り、”とありました。
もともと瘀血を持っていたご婦人が相手なんです。
瘀血というのは長期間持っていると「熱化」する性質を持ちます。
瘀血の背後に「熱」があると、血が蒸されてますます瘀血を形成する、という病理があるので
(べったりした液体を加熱すると、固形物が残りますね。残った固形物が瘀血というイメージです)
ただ瘀血を壊して下すだけでなく、帯びている熱を散らしてあげないと古い瘀血は取れないよ、という意図でしょうか。
この「透達」の作用からなのか牡丹は清熱涼血だけでなく「活血散瘀」つまり停滞している血を散らして巡らせる作用も併せ持っているんだそう。
ちなみに「行瘀」(停滞している瘀血を散らす)の作用は、桂枝茯苓丸に一緒に入っている「桂枝」も実は持っている作用。
しかしこちらは「温性」、つまり温めて巡らせるんですって。
ここまで「破瘀行血」の桃仁、「清熱涼血して活血散瘀」する牡丹皮について学んできました。
桃仁と牡丹皮だけ見ると、強烈に瘀血を下してしまいそうな感じがしますが、桂枝茯苓丸の方意は
“服法甚緩、以深固之邪、止堪漸以磨之也”
服法甚だ緩やか、深固の邪、ただ漸(だんだん)と以て之れを磨(減ずる)に堪(すぐれ)るを以て也
(『金匱鉤元』朱震亭)
と述べらるように、あくまで「緩やかに」瘀血を消していくということ。
(じゃないと妊娠中になんか、おっかなくて使えないですよ)
蜜で丸剤にしてしまうのもそのためらしいです
この方剤は名前の通り桂枝と伏苓が入っています。
瘀血を下す方剤ではありますが、桂枝と伏苓が、本来主役なんだそうです。
次回は桂枝と伏苓について書いてみます。
赤芍については、本当は桃仁・牡丹とペアで語られるべきものなのですが、これものちのち補足で書いていきます。
(参考文献)
『中国基本中成薬』(人民衛生出版社)
『金匱要略講話』(大塚敬節先生)
『漢方概論』(藤平健先生・小倉重成先生)
『神農本草経解説』(森由雄先生)
『中医臨床のための方剤学』(神戸中医学研究会)
『中医臨床のための中薬学』(神戸中医学研究会)
・・・(おまけ) ・・・
『神農本草経』の条文に出てくる、
「瘈瘏痙」「驚癇」は痙攣するような病気を指すんだそう。
ちょいと、勝手な深読み。。。
「瘏」。
これで「と」と読みます。
(参考文献の『神農本草經解説』では病ダレに従の字ですが、これは「瘏」の俗字なんだとか。)
「瘏」には、病む。病み疲れる。という意味の他に「馬が疲れて進めぬこと」「おそれる」という意味もあるんですって。
「瘏悴(とすい)」で、病み疲れるという意味になり、「瘏痡(とほ)」と書いて、病み疲れて行けないこと、という意味にも。
このあとの条文の通り、牡丹は「除癥堅瘀血」ですが、瘀血を形成する原因の一つに「疲れすぎ」というのもあります。
疲れすぎは、東洋医学の世界で「筋」や「謀慮(はかりごと=つまりは考え事、頭脳労働)」を主る「肝」の臓で「気の停滞」が起こる「肝鬱」という現象となって現れますが、牡丹皮は肝鬱の治療方剤のひとつ「逍遥散」に山梔子と共に加わることで「加味逍遥散」となり、肝鬱からさらに熱所見が発生する肝鬱化火の治療薬として活躍します。
加味逍遥散は時代が下った北宋時代(960-1127)に発明され、現代でも非常にお見掛けする方剤ですが、逍遥散に加える清熱薬の中であえて牡丹皮が選ばれたのも、この『神農本草経』の含蓄があるんでしょうか…??
(参考文献)
『大漢和辞典』(諸橋轍次 主篇)